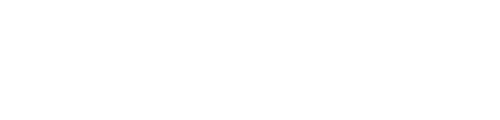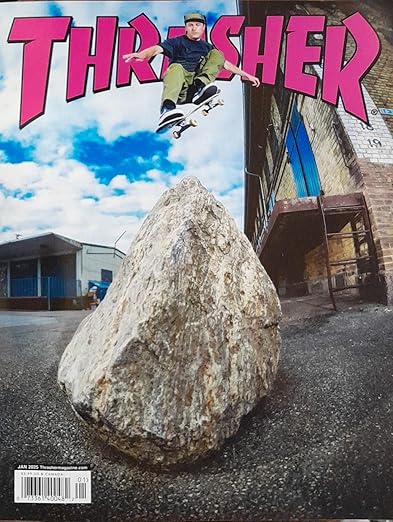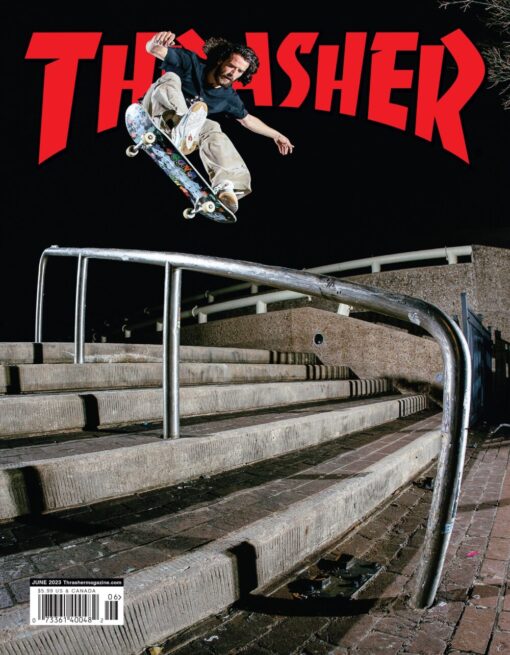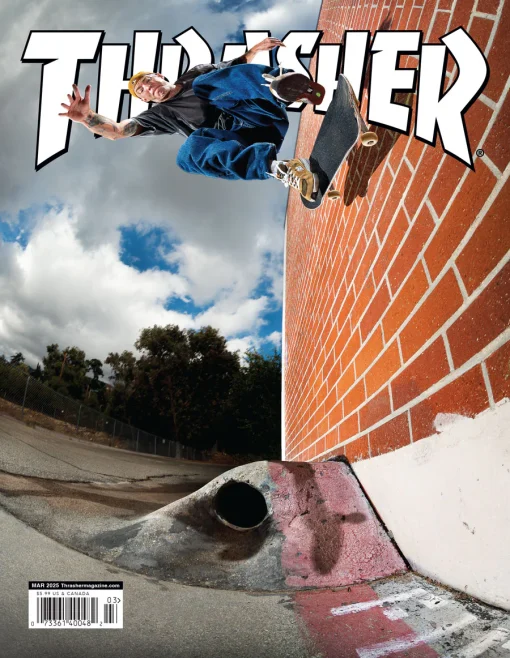街中にあふれる「スラッシャー」への違和感
最近、雑貨屋とかファッション系のセレクトショップで「THRASHER(スラッシャー)」のロゴをよく見かけるようになった。

Tシャツ、キャップ、バッグ……
けど、それを身につけてる人たちが、スケーターかというと、正直ちょっと違う。
いや、別に「着るな」とは言わない。
でもスケーターからすると、あのロゴには特別な意味がある。
だからこそ、「スラッシャーって何?」って聞かれたらちゃんと答えたくなる。
THRASHERとは何者か? スケートマガジンの始まり
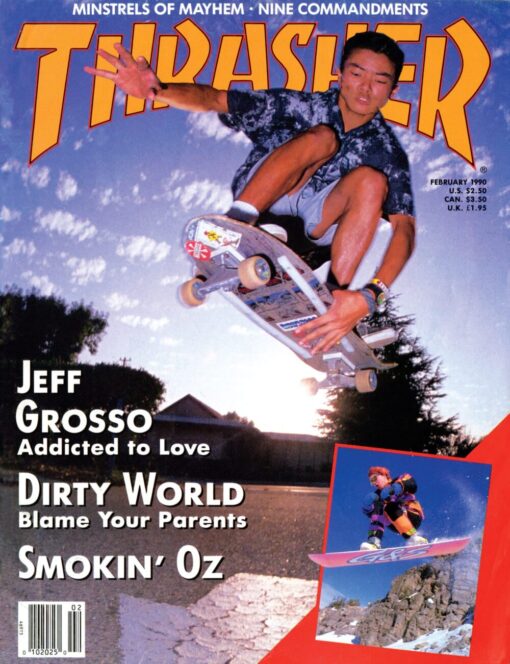
THRASHER(スラッシャー)は、1981年にアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコで創刊されたスケートボード専門雑誌。
創設者はEric Swenson(エリック・スウェンソン)とFausto Vitello(ファウスト・ヴィテロ)という、インディペンデントトラックカンパニーの創業者たち。
そのスタンスは最初から一貫していて、
「広告のためじゃない」「流行のためじゃない」——
リアルなスケーターのためのリアルな情報”を届けることに全振りしていた。
それら全部が“本物”。
単なる媒体というより、カルチャーそのものだった。
スラッシャーが築いたスケートカルチャーの中心
90年代〜2000年代に入る頃には、スラッシャーは世界で最も影響力のあるスケートメディアとして完全に確立。
特に有名なのが、毎年選ばれる「Skater of the Year(SOTY)」。
“その年一番ストリートを震わせたスケーター”をスラッシャーが独自に選出するアワードだ。
SOTYを獲ること=スケーターとして伝説になる、ってこと。
スラッシャーのロゴを着てるってことは、
「自分はこのカルチャーの文脈を知ってる」「敬意を持ってる」っていうサインでもあった。
なぜスラッシャーはかっこいいのか?
THRASHERのロゴを着るっていうのは、
「自分はスケーターです」って名乗るようなものだった。
これは単なるアパレルじゃない。
滑りまくって、こけまくって、路上で自分を削ってる人間だけが着る資格がある、ストリートの勲章。
だから、自然と“スラッシャーを着てる人”にはリスペクトがあった。

本気で滑ってるスケーターにとって、あのロゴは誇りだったんだ。
日本での“ファッション化”への違和感

でも、今の日本ではその意味が少し変わってきてる。
スラッシャーのロゴがファッションアイコンとして独り歩きして、
スケボー未経験の人たちが「かわいいから」「流行ってるから」と雑貨屋で普通に買っていく。
それを否定するつもりはない。
でも、ちょっとモヤっとするのも正直な気持ち。
だってスラッシャーって、ただのロゴじゃないから。
ファッションブランドじゃなくて、“スケーターたちの魂”そのものなんだ。
本物を知ってほしい。スケーターからの提案

もしスラッシャーのアイテムを身につけるなら、
ちょっとでいいからその背景を知ってみてほしい。
そうすると、きっとあのロゴの“重み”が変わってくる。